Table of Contents
今日のお悩み
帰国子女受験をするにあたり
語学以外に必要なこと

こんにちは!
講師のまみです。

こんにちは。
海外に住んでいる受験生ママです。

子供に帰国子女入試を受けさせる予定です。
英語をとにかく頑張れば良いですか?

勿論、語学は重要です。
ただし今日は「学校が語学以外に求めていること」について
お話し致します!

突然ですが、なぜ帰国子女入試は存在するのでしょうか?
勿論、日本の義務教育を受けていない子供に対する救済措置的な面はあります。
でもそれだけではないですよね。
帰国子女入試を行うことで「学校にメリット」がある、
だから帰国子女入試は存在します。
ではそのメリットとは、なんでしょうか😊✨
そのメリットを確認するために、帰国子女入試を行っている学校のHPををみて見たいと思います。

こちらのHPをチェック!
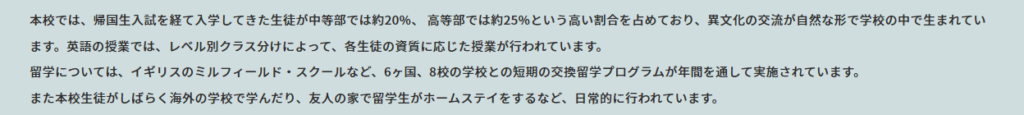
(慶應湘南藤沢中HPより)
こちらは国際色豊かな点を売りにされている慶應湘南藤沢中のHP抜粋です。
「帰国子女生徒が中学部では20%占めており、
異文化の交流が自然な形で学校の中で生まれる(中略あり)」とありますね。
まさに、この部分に学校側の帰国子女への期待が隠されています。
そもそも「異文化交流」とは、自分の文化とは異なる文化を持つ人々と交流し、
お互いの価値観や習慣、考え方を理解し合うことです。
互いに違いを尊重し、共に学び合うことで、
通常では出てこなかった新しい視点や発想を得ることができますからね!
学校側が求めたいのも理解できます。
しかしながら、本当の外国人を入学させても、言語の壁があります。
また価値観が異なり過ぎて、互いの理解に時間がかかります。
一方、日本語をしゃべることのできる・海外感覚をもつ帰国子女生なら、
海外生よりも身近な存在で、すぐに打ちとけられますよね。
そんな存在を学校内に取り入れることで、
学校内でプチ仮想国際空間(造語です😊💦)を作ろうとしているんですね。
そうなってくると、学校側が帰国子女生徒に求めることが見えてきます。
「英語のできる生徒」
…ではなくて!(勿論語学ができるに越したことはありません!そこが不要という話ではないです💦)
「海外に住んでいたからこその思考様式・視点を持っている生徒」
ちょっとフランクに言いかえるなら…
「へー!そんな考え方あるんだ!俺じゃあ思いつかないわ!さすがだわ!」って
同級生に言われる生徒さんが、求められてくるんですね。
プチ仮想国際空間を作るために、
多様なバックグラウンドをもった生徒を混在させる。
その多様な価値観勢としての役割が期待されているわけです!
つまりこれから帰国子女入試を受ける生徒さんには、
日本に住んでいたら至らなかったであろう思考様式を
身に着けてほしいなぁと思っています✨

学校側が求めているポイントはありましたが、
「日本に住んでいたら至らなかった思考様式」って
具体的になんでしょうか?
このようにお考えになる方も、いらっしゃるかもしれません。
この点について、お答え致します。
まず現在通われている海外の学校(日本人学校含む)と、
日本で通っていた(もしくは通う予定だった)学校を比較してみてください。
恐らく人数規模や、イベントの有無、主要教科以外の授業内容に
大きな違いがあると思います。
試しに人数で比較してみましょう。
日本の一般的な学校は、
35人学級、クラスは3~4組、イベントは学年単位(つまり150人前後で行う)というイメージでしょうか。
それに比べて、我が家の場合(イスタンブールの日本人学校)でいえば
3~5人学級、クラスは当然1組、イベントが学校単位(小中学年合わせて30人)です。
この差は歴然です。そしてこの差は、子供の思考様式に大きく関わります。
ここからは、少し我が家の話を織り込ませて頂きます。
先日、子供の学校で学習発表会がありました。(昔で言う学芸会でしょうか)
先生方のご尽力もあり、子供達が堂々と発表する姿が印象的な素敵な会で、
大変感動して泣いてしまったのですが…😢✨
…単に感動しましたよ!という話ではなく、
ここで一体何に感動したのか、という点が、
帰国子女入試をお考えの保護者様に役立つポイントになります。
先ほどに書かせて頂いた通り、我が子の学校は超少人数規模校。
よって生徒一人が負担する役割が、必然的に多くなります。
例えば劇に焦点を当てると、日本の35人学級だと、一人あたりのセリフが1言程度だったであろうところ、
少人数が故に、大変多くのセリフが回ってきて、子供達は長時間スポットライトを浴びることになります。
また一人で何役も兼任することもあります。
ここから得られる経験値って、抽象化すると、凄い素晴らしいもの、
そして帰国子女入試で求められるものなんです。
日本の大多数の中の、いち個人であれば、
「自分一人くらいサボっても、何とか回る」精神が育ちやすい。残念ながら。
しかし海外に出てくると、そうもいっていられない。
なぜなら個人が目立つ機会が沢山与えらるからです。
その経験を重ねる中で、子供達は
「自分が欠けたら全体が回らない。絶対に気を抜けない責任感を感じた経験」
「一人の行動が、全体の成果を大きく左右する環境で尽力した経験」
「多岐にわたる役割を経験し、マルチタスクの力を得た経験」
「限られた人数で成果を出す、限られた財源を最大限に生かした経験」
こういった価値ある経験ができているんですね。
そしてこの経験を経ている子達は、
日本に戻った後にも、自然と、この経験値を基とした意見をしてくれるようになります。
これこそが「日本に住んでいたら至らなかった思考様式」につながるわけです。
ここまでお話ししてきましたが、
この話題の中で一番重要なポイントをお伝えしたいと思います。
それは…

子供は、貴重な経験をしていることに、気づかない
ということです。
子供というのは、自分を客観視することが未熟なため、
今現在の自分=世の中のスタンダードと、当然とらえがちです。
どれだけ貴重な経験をしても
どれだけ恵まれた環境にいても、
彼らにとっては「これが普通」になってしまうんですね。
そこで重要なのが、保護者の役割です。
先ほどの学習発表会の例のように、
今行っていることが、いかに通常とは異なり、貴重な経験値なのか、
それを家庭内で褒め、ぜひその経験を抽象化してあげてください。

帰国子女の作文では、
海外で得た経験を作文にしていく必要があります。
この時に、鉄板ネタを作っておくと楽なのですが、
生徒だけでは、自分が貴重な経験をしていることに気づかず、
ネタ探しに詰まることが多いです。
よって授業では保護者様にもご協力頂き、
ネタ探しを行うことが多いです。
お手数をお掛け致しますが、是非ご協力お願い致します✨
それではここまでお読み頂き、ありがとうございました!


